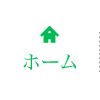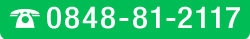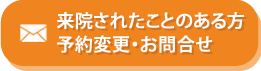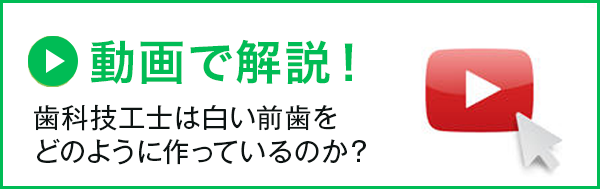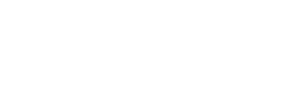スウェーデンにはなぜ「寝たきり老人」がいないのか
最後まで人生を楽しむ
「この施設には40人ほどのお年寄りが暮らしています。8割以上が認知症を患っていますが、寝たきりになっている人は一人もいません。自分の力で起き上がれない人でも、毎朝必ずスタッフが手伝って車椅子に乗せます。そして食堂で一緒に食事を楽しむのです」
こう語るのは、スウェーデンの首都ストックホルム郊外にある、介護サービス付きの特別住宅で働く介護士のアンナ・ヨハンソンさん。この住宅に暮らす人たちは、ほとんどが80歳以上のいわゆる後期高齢者で、在宅で介護サービスを受け続けることが難しいほどの要介護状態にある。
しかし、車椅子に乗っている人でもきれいな服に着替え、パジャマでうろうろしているような高齢者はいない。日本の後期高齢者が集う施設に比べるとずっと穏やかで、明るい雰囲気だ。
「ここでは、何より本人の意思が一番に尊重されます。散歩に出るのでも普通は誰かが付き添いますが、どうしても一人で散歩したいという人がいれば、家族の同意のもと、GPS付きの携帯を持たせて出かけるのを許可します。それで本人が事故に遭ったとしてもあくまで自己責任なので、施設の責任が問われることはありません。
もちろん、ベッドにしばりつけるようなこともありません。私たちが行うのは介護であって拷問ではないのですから。アルコールを飲みたいという人には、よほど健康上の理由がない限り、飲ませます。最後まで人生を楽しめるように助けるのが、私たちの仕事なんです」
高福祉国家として知られるスウェーデンは、OECD(経済協力開発機構)が行う国別幸福度ランキングでも上位の常連だ(’13年度はオーストラリアと並んで1位。日本は21位)。
スウェーデン人の平均寿命は81.7歳。日本人の83.1歳に比べれば短いが、それなりの長寿国である。にもかかわらず、この国には寝たきりになる老人がほとんどいないという。
「胃ろう」は虐待になる
独立して生活している高齢者が体調を崩し、誰かの世話が必要になった場合でも、家族が全面的に介護することはありえない。
「コミューン」と呼ばれる市町村にあたる自治体が高齢者の希望に沿う形で、サービスを提供することになっている。そして介護は在宅サービスが基本だ。
「日本では要介護認定されれば、在宅サービスを利用してもいいし、施設サービスを利用してもいい。これは、当該の高齢者や家族が自由に選べる『選択モデル』です。
一方でスウェーデンでは要介護状態になったら、できるだけ在宅での介護が行われます。介護付きの特別住宅に入りたいと申請しても、それを認めるかどうかは『援助判定員』というコミューンの専門職員の判断に任せられる。本当の人生の終末期にしか施設に入ることが許さない、『順序モデル』が基本なのです」(前出の西下氏)
「順序モデル」が取られているせいで、日本だったら確実に施設に入っているような認知症の高齢者でも、在宅介護が行われる。症状や要介護状態に応じて、一日に5度も6度も介護士がやってきていろいろと面倒を見るというケースが一般的だ。65歳以上の高齢者で特別住宅に暮らしているのは6%。つまり、高齢者の9割以上は自宅で暮らしている。
スウェーデンがここまで在宅介護と順序モデルにこだわるのには、2つの理由がある。1つは先ほども述べた「自立した個人」を尊ぶ文化。できるだけ最後まで自分の家で自分の力で暮らしたい、暮らしてほしいという考え方からくるものだ。

そしてもう1つは財源の問題だ。スウェーデンでは、介護の財源はすべて税金でまかなわれている。老人になれば誰でも少ない自己負担(上限が月1780クローナ=約2万5600円)で、介護サービスを受ける資格がある。
ただし、いくら税率の高い高負担国家でも、老人の面倒をすべて税金で見るのは限界がある。施設で24時間介護を行うよりも、在宅で何度も介護士を派遣するほうが結局はコスト的に安く上がるため、在宅介護が推奨されるのだ。
だが、そのことが結果として寝たきり老人の発生を防いでいる。寝たきりになってしまえば在宅介護は不可能になるからだ。
従って、介護士たちはできるだけ高齢者が自立した生活を送り、自分の口で食事をできるようにサポートする。国際医療福祉大学大学院の高橋泰教授が語る。
「スウェーデンを始めとした北欧諸国では、自分の口で食事をできなくなった高齢者は、徹底的に嚥下訓練が行われますが、それでも難しいときには無理な食事介助や水分補給を行わず、自然な形で看取ることが一般的です。
それが人間らしい死の迎え方だと考えられていて、胃に直接栄養を送る胃ろうなどで延々と生きながらえさせることは、むしろ虐待だと見なされているのです」
国を一つの「家族」と考える
現在の日本の病院では、死ぬ間際まで点滴やカテーテルを使った静脈栄養を行う延命措置が一般的。たとえベッドの上でチューブだらけになって、身動きが取れなくなっても、できるだけ長く生きてほしいという考えが支配的だからだ。
しかし、そのような日本の現状を聞いた冒頭のヨハンソンさんはこう語る。
「スウェーデンでも’80年代までは無理な延命治療が行われていましたが、徐々に死に方に対する国民の意識が変わってきたのです。長期間の延命治療は本人、家族、社会にとってムダな負担を強いるだけだと気付いたのです。
日本のような先進国で、いまだに無理な延命が行われているとは正直、驚きました」
北海道中央労災病院長の宮本顕二氏は、「スウェーデンの終末医療が日本と根本的に違うのは、たとえ施設に入っても原則的に同じ施設で亡くなるという点にある」と語る。
「日本の場合だと介護施設に入っても、病状が悪化すれば病院に搬送され、本人の意思にかかわらず治療と延命措置が施されます。施設と病院を行ったり来たりして最終的に病院で亡くなるケースがほとんどです。自宅で逝きたいと思っても、延命なしで看取ってくれる医師が少ない。
一方、スウェーデンではたとえ肺炎になっても内服薬が処方される程度で注射もしない。過剰な医療は施さず、住み慣れた家や施設で息を引き取るのが一番だというコンセンサスがあるのです」
介護する側もされる側も、寝たきりにならないように努力をする。それでもそのような状態に陥ってしまえば、それは死が近づいたサインだということで潔くあきらめる。それがスウェーデン流の死の迎え方なのだ。
このような介護体制を根底から支えているのは、充実した介護福祉の人材である。介護士は独居老人の家を頻繁に回り、短い場合は15分くらいの滞在時間でトイレを掃除し、ベッドメイクを済ませ、高齢者と会話をして帰るというようなことをくり返す。
日本では介護というと、どうしても医療からの発想になりがちで、手助けよりも治療という対処に傾きやすい。
最後までお読みいただきありがとうございます。
広島県三原市の歯医者 大名歯科
Author Profile
- 大名 幸一 Koichi Omyo
Latest entries
 健康2025.04.03酸で歯がボロボロ!?意外な黒幕は大手製薬会社だった!
健康2025.04.03酸で歯がボロボロ!?意外な黒幕は大手製薬会社だった! 健康2025.04.02甘いものより危険!? “ダラダラ食べ”が歯を滅ぼす!
健康2025.04.02甘いものより危険!? “ダラダラ食べ”が歯を滅ぼす! 歯科2025.04.01歯は食器より脆い!?“噛むスピード違反”で歯が割れる理由
歯科2025.04.01歯は食器より脆い!?“噛むスピード違反”で歯が割れる理由 虫歯2025.03.31虫歯になる歯医者に診てもらう恐怖!“敗者”にならないための選び方
虫歯2025.03.31虫歯になる歯医者に診てもらう恐怖!“敗者”にならないための選び方
この記事をFacebookでシェアする